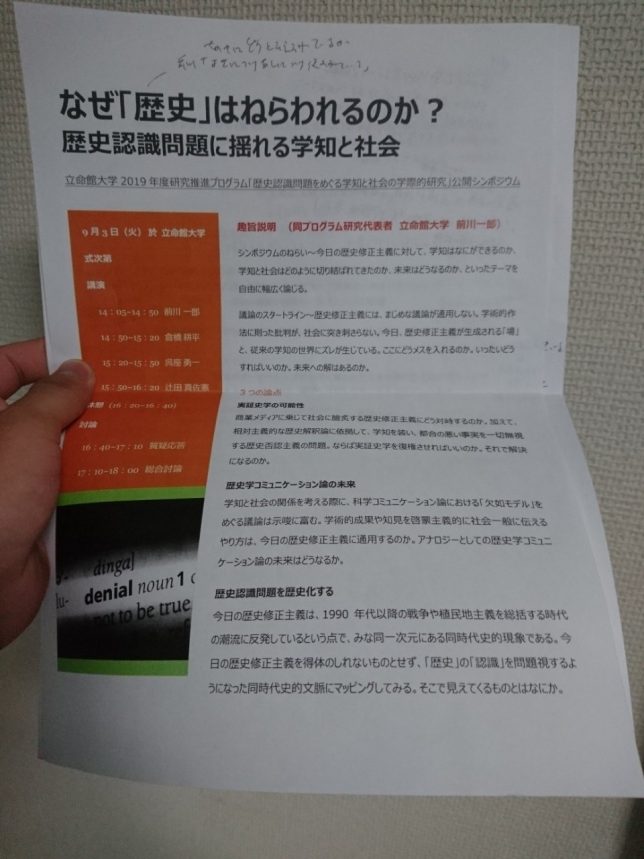
歴史修正主義的な言説がはびこる社会を前に、学知は何をなすべきかを主題とした公開シンポジウム「なぜ『歴史』はねらわれるのか?─歴史認識問題に揺れる学知と社会」が3日、立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)であり、後輩も誘って聴きに行ってきた。前川一郎、倉橋耕平、呉座勇一、辻田真佐憲(登壇順)という豪華なメンバーのそろい踏みでとてもおもしろかった。
各者の講演それぞれが呼応し合っていて、よく構成が練られたシンポジウムだったと思う。
前川さんは、歴史修正主義をそれが顕在化した1990年代の同時代史的な文脈に位置付ける試みを展開。冷戦体制の崩壊と旧植民地国の地位向上、人権概念の広まりを背景とした戦争・植民地主義総括の動きが高まり、戦後の旧宗主国と旧植民地国の間の「手打ち」によって確立された国際秩序体制とそれに組み込まれた「国民史」が問題とされる時代に入り、現在も続いている。ところが実際には旧植民地側からの戦時補償の訴えを、旧宗主国側が受け入れて補償実現に至る例はほぼないし、「国民史」に都合の悪い事実に関して権力が拒否するという構図は続いており、歴史修正主義言説がこれに付和雷同しているという見立てだった。
倉橋さんは、文化生産者による評価が重視される歴史が学知で、文化消費者による評価が重視される歴史が歴史修正主義だという位置付けのもと、「歴史修正主義は歴史学にとって問題だが、歴史学の問題ではない」として社会学的なアプローチの必要性を訴えた。特に歴史修正主義側が、「正しい歴史」の追求ではなく、敵味方の二項対立や人権問題の隠蔽などを目的に「歴史を確定させない」ことを狙っているのではないかという指摘はとても腑に落ちる部分がある。と同時に「あくまで仮説」と断りを入れながら、昨今、自己啓発書を多く手掛けてきた出版社からも歴史修正主義的言説の書籍が登場するようになったことを例に、自己のアイデンティティーを保つためには、「歴史」は書き換えられても良いという、「歴史」の道具性を示唆する見方が提示されていて、社会学らしい視野からの鋭い考察ではないかと感嘆した。ぜひ実証に挑んでほしい。
呉座さんは現在の歴史認識問題が、晩年の網野善彦が、いわゆる「つくる会」の自虐史観批判と対峙した時代とほぼ構図が変わっていないのではないかという視点で語った。網野は、日本共産党がバックに付いた1950年代までの「国民的歴史学運動」を「政治主義による学問の引き回し」と総括した戦後歴史学が、同運動のトラウマを引きずり続け、アカデミズムにとじ込もったり、ナショナリズムに利用されることへの過剰な危機感を持つがゆえに歴史学の可能性を狭めたのではないかと指摘していた。こうした文脈を元に、「歴史が利用されることは果たして歴史学が悪いのか」という問題提起をした。これは倉橋さんの「歴史修正主義は歴史学にとって問題だが、歴史学の問題ではない」と重ね合わせになっている。つまり裏を返せば、歴史認識問題への対処が学際的な課題として位置付けられるべきだとする、今回のシンポを主催した研究プロジェクトの意義を強調する形になっていて、僕もこれには大いに同意するところだ。
辻田さんは、歴史修正主義への対抗策として、歴史修正主義側が「物語」を武器とすることに対応する形で、「物語」をより実証史学も納得しうる形でアップデートすることを提案した。その実践として、森友学園の幼稚園で軍歌を歌わせたり教育勅語を暗唱させたり、教室に天皇の御真影を飾ったりしていたことが報道された際に、そうした行為は戦時中なら不敬罪に問われかねないことから、極めて戦後的文脈に即した「二次創作」だと論評した記事を紹介していた。そうしたフレーズと物語を活用した対抗は、在野の作家・ジャーナリズムが得意とすることであると同時に、専門知と連携しうるものであるという主張だった。
この後の討論は「歴史はなぜねらわれるのか」という問いと「歴史学はどう立ち向かうべきなのか」という問いが混然としていて、言ったり来たりするきらいはあったのが難点だったかなとは思う。また指摘されていたように、まだまだこのシンポも「市民に開かれた」とは言い難かったり、歴史修正主義が人権問題の隠蔽を目的としている可能性がある以上、そうした観点からの研究者も参加させるべきではないかとも思った。聴講側にいた牟田和恵さんが最後に発言して「歴史学の在り方だけでなく、歴史の使われ方にも着目していくべきだ」と言っていたのは全く同感である。